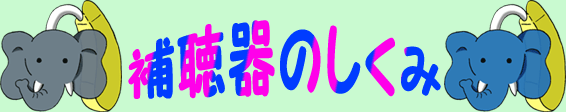
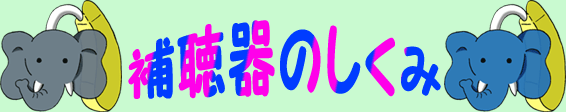 |
| ���|�����⒮�� | 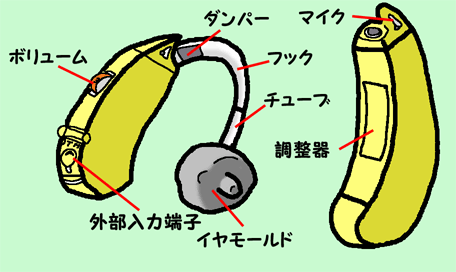 |
|||
| �������⒮�� | 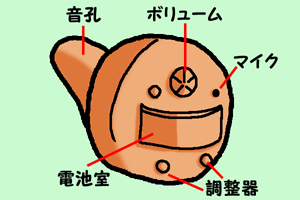 |
|||
�Ȃ��A���G�ł悭�킩��܂���ˁB�ȒP�Ȑ}�ɂ��Ă݂�Ɓc
| ���Ƃ����Ă��邩�������Ȃ��� | �⒮����g���� ��������� |
�킩�����I�I�w��x���I |
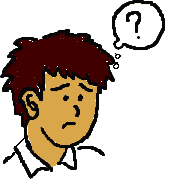 |
�⒮���t���āA�@�@�X�C�b�`�I���I |
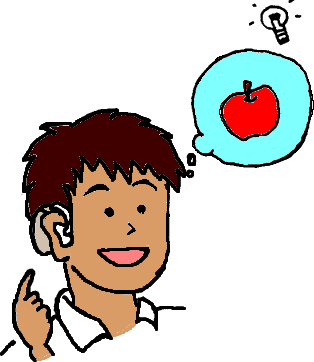 |
����͢�}�C�N���t�H����ł���}�C�N���t�H���͉����W�߂ĕ⒮��ɓ���铭�������܂�����Ɠ��������ł��ˡ
�@����,�����̐l���g���Ă���⒮��̃}�C�N���t�H���͢���w����(�ނ����������j�}�C�N���t�H���v�Ƃ����Ď���ɂ��邢�낢��ȉ�����W�߂Ă��܂��܂��
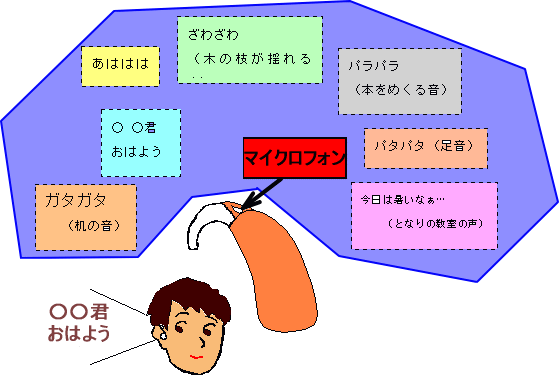
| �@���낢��ȉ��̒����� |
�u |
�݂Ȃ��g���Ă���⒮��ɂ�,�������̒����킪���Ă��܂���}�̂悤���܂݁y�g���}�[�z��,�⒮��ɂ���������܂��ˡ����͂��̒��̈��,����������i�����傤�������j�ɂ��Đ������܂��
����������͉��̍��������ĉ�����₷�����܂���⒮��̋@��i������j�ɂ���Ĉ�i�����j���܂���,�m�y�S���i����j�z�̈�Œ������邩,�g�y�����i��������j�z���k�y�ቹ�i�Ă�����j�z�̂Q�Œ���������̂������ł���Ⴆ�c
���|���^�⒮��̗�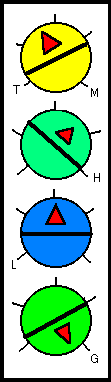 |
|
|||||||||||||||||||||||
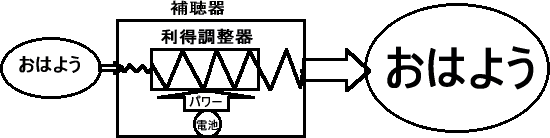
| �@�C�����[���h�Ƃ́A�������^��{�b�N�X�^�� �@�g�̂��傫���Ȃ�Ǝ��̌����傫���Ȃ�܂��B���̂��߃C�����[���h���҂����肵�Ȃ��Ƃ��A �����n�E�����O����悤�ɂȂ�����A�C�����[���h�����ւ��鎞���ɂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B �ŋ߂ł́A�C�����[���h�����Ƃ��ɁA�D���ȐF��I��A�����ȃV�[���𒆂ɓ��ꂽ�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�@�Ƃ���ŁA���Ȃ��̃C�����[���h�͉���Ă��܂����H�C�����[���h������Ă���ƁA�������ɂ����Ȃ�����A �@�@����f�[�^�ɂ��ƁA�����g���Ă���⒮���l�H������ |
�ϐg�I�I 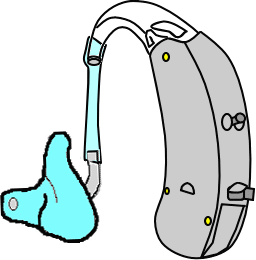 �l�̂��� �������ꂢ�� ���Ă� |
||||||||||||||
| �@������ �u���Ȃ��̃C�����[���h�����x�`�F�b�N�I�I�v |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| �C�����[���h�̑|��(������)���@(�ق��ق�)�� �@�ʂ�ܓ��ō�������(���傤)�t(����)�ɂ��炭 �Z(��)���A ���̒����A�₳�����U(��)����܂��B ��(�悲)�ꂪ�Ђǂ��Ƃ��͎���(������)�u���V���g�p���܂��B ���̌��B���ꂢ�ɂ������� �C�e�B�b�V���Ő�����@�����܂��B �i�݂�Book�������Ă���l�́u�⒮��̃N���[�j���O���@�v�̃y�[�W���Q�l�ɂ��Ă��������B�j |
|||||||||||||||
| �@�@ ���E���I�ł��ڂ��̃C�����[���h�I�H |
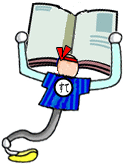 |
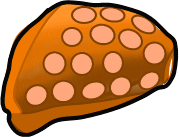 |
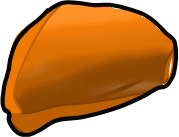 |
�@GN���T�E���h�Ђ��甭�����ꂽ���^�������⒮��ɂ́A (2011.12���݁j �@�ł��ڂ������邱�ƂŁA�畆�� �@����A�F���g���⒮��̃C�����[���h�ɂ��A�L�����Ă��邩������܂����B |
| �V���� �f�B���v���E�V�F�� |
����܂ł� �m�[�}���E�V�F�� |
|
|
|||
| ����́A���|���^�̕⒮��̃t�b�N�̒��ɂ����u�_���p�[�v�ɂ��Đ������܂��B �i�⒮��ɂ���Ă̓t�b�N�̒��Ƀ_���p�[���Ȃ��^�C�v������܂��B�j | |||
| �@�_���p�[�́A�t�b�N�̍���(�˂���)�⒮��ɐڑ����镔���̂�����ɓ����Ă��܂��B����2�o�̏����ȓ���i���傤�j�̕��ł��B ���̒����悭�悭�̂����Ă݂�ƁA�ƂĂ��ׂ����Ԃ����������Ă���̂������܂��B �@ |
�l�̂�����Ă�t�b�N�� �����Ă���� 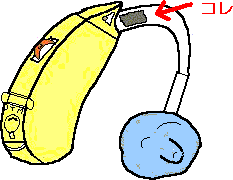 |
||
�_���p�[�������Ă���ƁA�⒮�킩��̉��������_(���)�炩�������ɂȂ�܂��B �t�Ƀ_���p�[�������Ă��Ȃ��ƁA���̎h�����������������ɂȂ�܂��B �⒮������̃O���t�ł��̈Ⴂ�����邱�Ƃ��ł��܂��B ���̕���������D�݂͐l���ꂼ��Ⴂ�܂��̂ŁA�⒮��̒���������Ƃ��ɁA���ۂɃ_���p�[�������Ă���ꍇ�ƁA �����Ă��Ȃ��ꍇ�Ƃŕ�����ׂĂ݂�Ɨǂ��ł��傤�B
�t�b�N�̒��Ƀ_���p�[������⒮��̏ꍇ�́A�u���V�ŃS�V�S�V��킸�A ���K�l�Ȃǂ�������g(���傤�����)���@(���傤��)�ŐƂ悢�ł��傤�B �w�Z�ɂ�����̂Ŏg���Ă݂Ă��������B
�_���p�[����t�b�N��600�~�A�_���p�[�Ȃ��t�b�N��200�~�ł��B
�@�����ԈႦ�ă_���p�[��(�ނ�)�ɂ��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A���ӂ��܂��傤�B
| �@����ȂƂ��C�⒮��Ɂu�O��(������)����(�ɂイ��傭)�[�q(����)�v�����Ă���ƁC���W�J�Z��d�b�@����C���ڃR�[�g���Ȃ��ŁC��������Ƃ��ł��܂��B�������邱�Ƃŋ�C���̎G��(������)�ɉe��(�������傤)����邱�ƂȂ��C���ꂢ�ȉ�������Ƃ��ł��܂��B�@ �u�O�����͒[�q�v�͂��ׂĂ̕⒮��ɂ��Ă���킯�ł͂��肹��B �u�O�����͒[�q�v���͂��߂�����Ă�����A��]�ɉ����Ă�������̂�����܂��B |
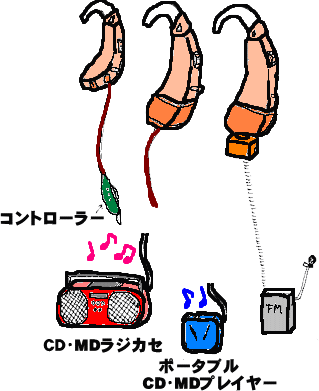 |
||
| �⒮��̂��̕����ɂ���s�i�e���R�C��)��l(�}�C�N)�͂ǂ�ȂƂ��Ɏg���̂ł��傤�� | 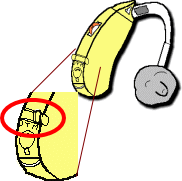 |
| �������^�̕⒮��̑����ɂ́A�X�C�b�`��T��M�̐�ւ������Ă��܂��B �s(�e���R�C��)�́A���[�v�V�X�e����d�b�y���d�b�����ȓd�b�̂݁z�ȂǁA �e���R�C����p��������傫�����܂��B���[�v�V�X�e�����ݒu����Ă��镔����{�݁i�����j�łs�i�e���R�C���j���g�p����ƁA ���[�v�V�X�e�����瑗���Ă��鉹�����Ƃ��ł��܂��B �܂�A����̉��Ɏז��i����܁j����邱�ƂȂ��A ��r�I�i�Ђ����Ă��j���āi�߂���傤�j�ȉ������Ƃ��ł���̂ł��B �@���[�v�V�X�e�����ݒu����Ă��鋳���ōs������Ƃł́A�s(�e���R�C���j�ɂ��Ă����Ɛ搶�̐��������₷���Ȃ�܂��B�⒮��̎�ނɂ���Ă͕⒮��̃}�C�N����̉��ƃ��[�v�V�X�e������̉��̑傫�����ł���⒮�������܂��B |
 |
|||
| �@ �@�l(�}�C�N)�́A�⒮��ɂ��Ă���}�C�N���t�H������̉���傫�����܂��B���i�̐����ł́A�l(�}�C�N)�ɂ��Ă����Ƃ悢�ł��傤�B �@�܂��A�u�l�s�v�Ƃ�����ւ�����������A�l��s�̑��u���Ȃ��⒮�������܂��B�����̕⒮����m���߂āA��ʂɍ��킹�Ďg���悤�ɂ��܂��傤�B |
||||
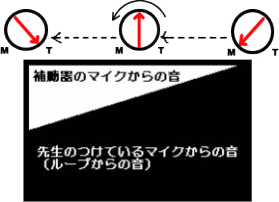 |
�@���[�v�̊O�ɏo�Ă��܂��ƁA���[�v����̉��͕⒮��ɓ���Ȃ��Ȃ�܂��B��������o��Ƃ��A�搶���}�C�N���O�����Ƃ��́A�X�C�b�`��M�ɐ�ւ��܂��傤�B�܂��A�̈�����c�t���̃v���C���[���A���w���̉�c���ɂ����[�v���\���Ă���܂��B�W��̎��A�⒮��̃X�C�b�`��T�ɐ�ւ��Ă݂܂��傤�B�搶���}�C�N���g���Ęb���Ă��鐺���������₷���Ȃ�܂��B |