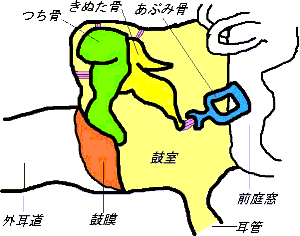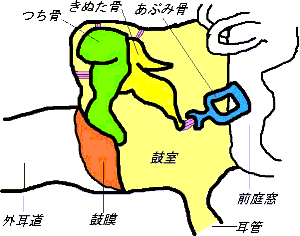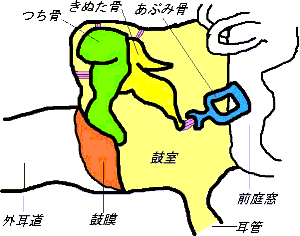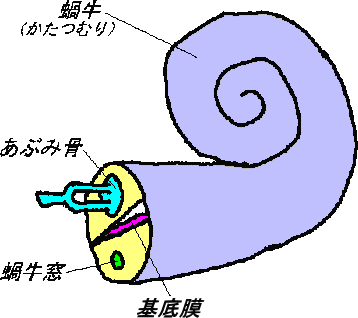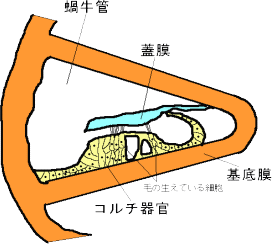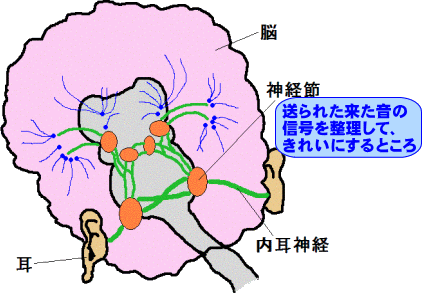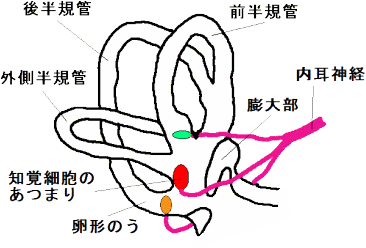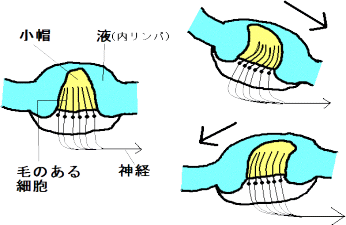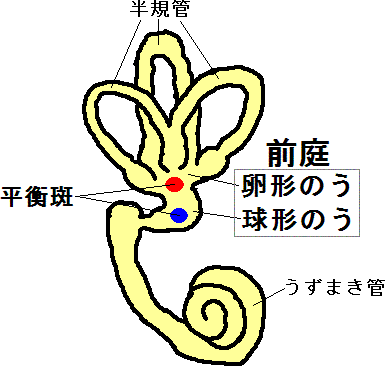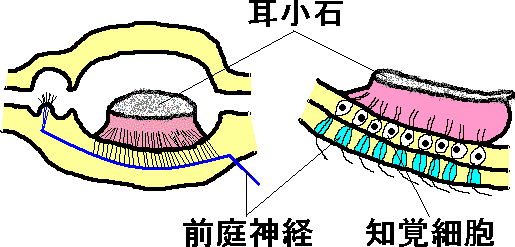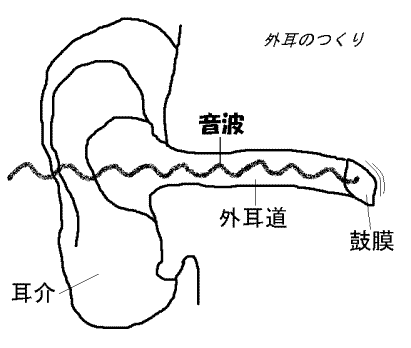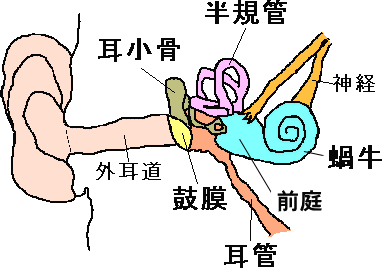耳で一番複雑な部分は『内耳』です。ここには、音を聞くのとつりあいをとるのと、2つの感覚器があります。内耳の部分のうち、「蝸牛」という部分が音を聞くとろこです。これは、かたつむりのように2周と4分の3巻いているうずまき形の管です。
頭がどの方向に傾いているのかを感じとるのは、3個の輪のような形をした管からできている「半規管」という部分です。それぞれの管のつけ根にはふくらみがあって、その中につりあいを感じる器官が入っています。3個の管が1つにまとまる部分は、2つの大きいふくらみになっています。この2つのふくらみは、頭の位置を知るところです。
内耳には、液がいっぱい入っています。この液は、音を感じる細胞のあるところまで、音の振動を伝える重要な仕事をしています。音の信号は、細胞で電気信号にかえられて、「聴神経」が電気信号を脳へ伝えます。
「外耳道」の形は人それぞれ違います。長さは約2.5cmと短く、とても薄い皮膚で覆われていて、表面にはこまかい毛が生えています。
外耳道の入り口の皮ふからねばねばした
「耳垢(じこう)」という脂を出しています。耳垢は、入ってくるゴミをとらえて、鼓膜(こまく)まで届かないようにする役目をしています。
外耳道のつきあたりに「鼓膜」があります。鼓膜は、うすい、ハート形の膜で、中耳への入口をふさぐようにはられています。
鼓膜は、とがったものを耳に突っ込むと、簡単に破れてしまいます。鼓膜は、中耳の中にある小さな骨と連結していて、外耳から中耳へと音の振動を伝えます。
外耳道から入ってきた音の波が、鼓膜にあたると、鼓膜ははげしく振動します。
これが『聞く』ことのはじまりです。
私達は普通、外から見える「耳たぶ(耳介)」を「耳」と呼んでいます。耳は外から見ると、簡単なつくりをしているように見えますが、実はその奥に複雑なしくみが隠されています。頭の両側にある部分「耳介」
は、音を集め、音の方向を聞き分ける重要な役割を果たしています。しかし、実際に「音」を知覚するのは、耳の奥の頭の中にある部分がやっているのです。
私たちの「耳」は、音を聞くほかに、体のつりあいをとったり、頭の傾きを感じたりする働きもあります。
振動は、中耳にある耳小骨(じしょうこつ)という3個の非常に小さい骨を通って伝わります。最初の骨は、つち骨と言います。鼓膜にくっついていて鼓膜と一緒に振動します。
つち骨は、次のきぬた骨を動かします。この骨は、鼓室(こしつ)と呼ばれる中耳の空洞の中で自由に動くことができます。ですから、槌骨から伝わった小さな振動は、きぬた骨にいくと50%も大きい振動になるのです。
きぬた骨の終わりは、いちばん小さいあぶみ骨についています。この骨は、前庭窓(ぜんていそう)とよばれる膜についています。前庭窓は内耳の入口で、鼓膜の振動は3個の骨を伝わって前庭窓に送りこまれるのです。
ここでは、壊れやすい鼓膜を守るために、中耳にある
安全装置(あんぜんそうち)について説明します。
鼓室(こしつ)の中には、空気が入っています。私たちが高い山に登ったり降りたりすると、外の空気の圧力が変わるので、鼓室の中の空気もひろがったりちぢめられたりします。この圧力の変化は、破れやすい鼓膜に力をかけて、傷つけたり、破裂させたりすることがあります。
これを防ぐために、中耳とのどをつないでいる耳管(じかん)という長い管があって、中耳の中の空気の圧力を外の空気の圧力と同じにしているのです。
中耳には、もう一つ安全装置があって、耳を騒音から守っています。
耳に、非常に大きい音が入ってくると、小さい筋肉がちぢんで鼓膜を強く緊張させ、鼓膜が大きく振動しすぎるのを防ぐのです。
また、もう一つの小さい筋肉が、あぶみ骨を引っぱって、きぬた骨とのつながりをゆるめて、前庭窓に伝えられる振動をやわらげます。
耳は、外耳・中耳・内耳の3つの部分にわかれていて、それぞれが特別な働きをしています。
『外耳』は、外から見える「耳介(耳たぶ)」と、それに続く長さ2.5cm、直径8mmくらいの管「外耳道」と、そのつきあたりにある「鼓膜」からできています。
鼓膜の内側の小さい部屋を『中耳』といいます。中耳には、3個の小さな骨 「耳小骨」があって、耳に入ってきた音を強めるしくみがあります。この部屋の中には、空気が入っていて、音は耳小骨を伝わります。
内耳は、鼓膜から中耳の骨を通って送られてきた振動を電気信号に変えて、神経から脳へ送る所です。
蝸牛(かぎゅう)は、振動を選び、ひろいあげる役目をする所です。奥に行くほど細くなっている、うずまき形の管で、カタツムリに似ています。
蝸牛は、3つの部屋に分かれ、3本の管がぴったりと並んでくっつきあっているようになっています
この細胞のある所はコルチ器官と呼ばれ、蝸牛管にすじのように走っています。コルチ器官には、蓋膜(がいまく)という非常に薄い膜があって、管の内側に続いています。この蓋膜のすぐ下に、知覚細胞の集まりがあります。細胞のひとつひとつに毛が生えていて、これが蓋膜に触れるようになっています。知覚細胞からは、それぞれ神経が出ていて、信号を伝えます。知覚細胞は、基底膜(きていまく)という蝸牛管の底にある膜の上に乗っています。
図は、蝸牛(かぎゅう)の一部を切って、コルチ器官(きかん)という知覚器を見たものです。
コルチ器官の上下の膜は、管の中の液が音波で振動すると、それにつれて動きます。
この膜の動きが、コルチ器官の知覚細胞(ちかくさいぼう)を刺激して、神経に信号を送るのです。
内耳では、音は液の振動に変えられて、伝わります。音波は、一番上の管の中を、細くなっている方に向かって伝わり、まん中の蝸牛管(かぎゅうかん)、下の管へと移ります。
そこで、波は管の太い方に向かって反対に伝わり、蝸牛窓(かぎゅうそう)の膜を振動させます。この仕事がすむと、音波は中耳の空気の中に戻されます。
音波が、蝸牛管の壁に伝わってくると、その振動がコルチ器官の下にある基底膜(きていまく)を動かします。すると、毛が生えている知覚細胞が、基底膜の振動にあわせて上下に動き、蓋膜(がいまく)に毛がさわります。これが刺激になって、知覚細胞の中に電気信号が起こり、神経を通って脳へ伝わるのです。
蝸牛の中を伝わる音波の振動の形は音の高さによって違うので、それぞれ違った場所の知覚細胞を刺激します。それで、脳は入ってきた音の高さを知ります。
また、大きな音が入ってくると、基底膜の動きが大きくなり、たくさんの知覚細胞が刺激されます。そこで、脳は大きな音が入ってきたことを知るのです。
蝸牛が受けとった情報は電気信号(音信号)に変えられて、耳から送り出されます。コルチ器官には23000個もの知覚細胞(ちかくさいぼう)があって、それぞれ信号を作り出しています。一つ一つの知覚細胞から細い神経線維(しんけいせんい)が出ていて、だんだん一緒に集まり、1本の神経の束になります。
音信号は内耳神経(ないじしんけい)を通って、脳へ行きます。この神経は、3万本位の神経線維の太い束からできています。
知覚細胞は、絶えず規則正しいかすかな信号を送り続けています。知覚細胞の毛が蓋膜(がいまく)にあたって細胞が刺激されると、音信号はとても速くなります。ですから、音の振動が知覚細胞に伝わると、音信号となり神経線維を通って脳に送られます。
かなりたくさんの音信号は、脳に伝わる前に失われてしまいます。しかし、これは悪いことではありません。このために、私達は聞く必要のない音信号(雑音)を感じなくてすむのです。つまり、脳に届く音信号は“こされて”きれいになっているといえます。
内耳神経は非常に短く、耳のすぐそばにある脳の神経節(しんけいせつ)に音信号を送ります。音信号は脳の中に入ると、込み入った道を通って脳の別の部分へ行きます。この道の途中で、信号の一部は反対側の脳へ移ります。これは多分、左右の耳に音が届いた時間のずれや、音信号の量の違いから音がやってきた方向を決めるためでしょう。
頭の動きを感じる器官を『半規管(はんきかん)』といいます。半規管は3個の半円形の管で、中に液が入っています。この3個の管は、一つは水平方向に、他の二つは垂直(すいちょく)方向(互いに直角にまじわる位置)についています。
体のつりあいを感じる感覚【平衡感覚】は、
耳の重要な働きの一つです。
この感覚は、二つあります。
ひとつは、頭の動きを感じる感覚。
もうひとつは、重力(どっちが上か)を感じる感覚です。
半規管の中の液の動きによって頭の動きを感じます。頭が動くと半規管も一緒に動きます。しかし、中の液はもとのまま止まっていようとする【慣性(かんせい)といいます】ので少し遅れて動き出し、小帽は動いた方と反対に曲げられます。これを知覚細胞に生えている毛が感じとって、細胞は信号を脳へ送ります。頭を動かす速度が速いほど小帽が強く曲げられ、たくさんの信号が脳に送られるので、頭がどれ位速く動いているかを知ることができます。また、どの半規管から信号が送られているかによって、頭がどの方向に動いているかわかります。
半規管のつけ根に
【膨大部(ぼうだいぶ)】という膨らんだ部分があり、この中に長い毛の生えた知覚細胞(ちかくさいぼう)が入っています。
毛の周りには小帽(しょうぼう)というやわらかい物質がかぶさっています。
頭の上下方向の動きと頭の位置を感じるのは、前庭器官(ぜんていきかん)です。ここには、球形嚢(きゅうけいのう)と卵形嚢(らんけいのう)という部分があり、中には平衡斑(へいこうはん)という特別な知覚細胞(ちかくさいぼう)の集まりがあります。
平衡斑は、長い毛をもつ知覚細胞のかたまりで、毛がまげられた刺激で信号を出します。平衡斑の表面はゼリーのような層におおわれていて、その中に耳小石(じしょうせき)という小さい粒がうずまっています。
体が傾くと、耳小石は元の位置を保とうとするので、動きにズレができ、細胞の毛がその刺激を感じて、脳へ信号を送り出します。また、耳小石が重力で引かれている方向を脳へ知らせるので、どちらが下かを知ることができます。
半規管や卵形のう、球形のうからの信号は、内耳神経(ないじしんけい)を通って脳へ送られます。脳から、脚、背中、首などの筋肉に命令が送られて、細かな調節をして、自動的に姿勢を直し、まっすぐ立ったり、ふらつかないで歩くようにします。これは、『反射(はんしゃ)』という運動で、私たちが気づかないうちに行われます。
「耳のしくみ」
〜音を集める〜
〜音を強める〜
〜鼓膜を守る安全装置〜
〜蝸牛(かぎゅう)〜
〜コルチ器官〜
「内耳から脳へ」
平衡感覚(へいこうかんかく) ①
中耳
内耳
外耳
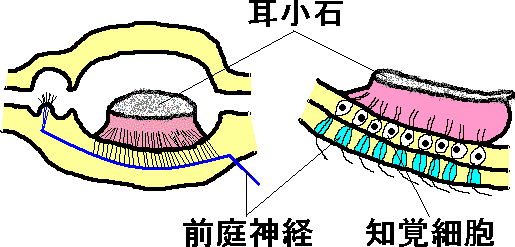
| 病名 |
原因 ・ 症状 |
対処法 |
耳垢栓塞
(じこうせんそく) |
耳垢腺(じこうせん)から出た粘液が脂やはがれ落ちた皮膚と混じって固まったものを耳垢といいます。耳垢はふつう自然に外耳道へ出ますが、出ずに外耳道をふさいだ状態をいいます。耳垢が耳の中にたまり、耳がふさがったような感じになります。 |
耳の穴の奥の高くなったところより手前を綿棒でふき取るように掃除します。耳
垢栓塞では自分で取ろうとして逆にもっと押し込んでしまったり、鼓膜や外耳道を傷つけたりするおそれがあるので、医師に取ってもらいましょう。 |
外耳道異物
(がいじどういぶつ) |
外耳道の中には狭くなったところがあり、そこを通って昆虫や植物の種が入ることをいいます。耳掃除などで傷ついた所に細菌が感染しておこります。 |
昆虫が入ったときは、あわてず耳の穴に懐中電灯などを使って光を当てて、誘い出す方法がありますが、医師に除去してもらう方がいいでしょう。 |
外耳道炎
(がいじどうえん) |
耳の通り道の炎症です。綿棒などで毎日耳掃除をしているとなりやすいです。耳の中が腫れたり耳だれが出たりして、かゆみ、痛みのほか、耳がふさがったような感じになります。 |
耳掃除をしばらくやめましょう。また、病院で診てもらい、抗生物質を飲んだり、点耳薬や軟膏を塗ったりすることで治ります。 |
急性中耳炎
(きゅうせいちゅうじえん) |
風邪をひくなどして、のどや鼻に細菌が入って炎症を起こすことがあります。その細菌などが耳管を通って中耳に入り、中耳の粘膜が炎症を起こすと中耳炎になります。突然耳が痛くなって、耳がふさがった感じになります。耳だれが出る事もあります。 |
抗生剤が効きますが、重症になると鼓膜切開症状が必要になります。長引くと「慢性中耳炎」になるおそれがあります。耳がおかしいと感じたら早めに耳鼻科に行きましょう。 |
滲出性中耳炎
(しんしゅつせいちゅうじえん) |
風邪やアレルギー性鼻炎などで鼻水や鼻づまりが続くと、耳管の開きが悪くなり、鼓膜の内側(中耳)に液がたまります。痛みはありませんが耳がふさがった感じになります。 |
鼻水がひどい場合は鼻の治療をします。また、中耳内にたまった液を出さなければなりません。鼓膜切開が必要な場合もあります。早めに病院へ行きましょう。 |
突発性難聴
(とっぱつせいなんちょう) |
ストレスやウイルス感染が原因と言われていますが、はっきりわかっていません。内耳の神経自体の障害で、突然聞こえが悪くなります。耳鳴りがしたり、耳がふさがった感じがします。 |
症状が出てから、早く治療を行えば治る可能性もあります。安静が必要です。症状が重い場合は入院して点滴などの治療を行います。 |
低音障害型突発難聴
(ていおんしょうがいがた
とっぱつなんちょう) |
原因は不明で、突然聞こえが悪くなります。聴力検査では低音部だけ聞こえが悪くなります。耳鳴りがしたり、耳がふさがった感じがします。 |
突発性難聴と同じような治療を行います。 |
音響外傷
(おんきょうがいしょう) |
コンサートなどで大きな音を聞き続けたり、耳の近くで大きな音を聞く事によって、音を感知する器官が損傷しておこります。 |
すぐに内耳の神経損傷に対する治療が必要です。大きな音を聴いたあとでおかしいなと感じたらすぐに病院に行きましょう。 |
| メニエール病 |
半規管や蝸牛のリンパ液が増えすぎて生じるといわれています。急にぐるぐると目がまわったり耳が聞こえなくなったりします。その他、耳鳴りや自律神経症状として吐き気や冷や汗、顔面蒼白の症状がみられます。 |
発作期には安静を第一にして、めまいを鎮めます。鎮静薬、鎮吐薬、抗ヒスタミン薬、ビタミン剤などを使用します。 |
外から見える外耳の部分を、
「耳介(じかい)」といいます。
耳介は、軟骨というゴムのような物質でできています。耳介は、音を集めやすい形をしていて、集めた音を「外耳道(がいじどう)」に送ります。
一番上の管のはじのふくらみには前庭窓(ぜんていそう)が、一番下の管には蝸牛窓(かぎゅうそう)があって、それぞれ中耳にひらいています。上と下の管の中には、外リンパという液がいっぱい入っています。まん中の管はずっと細くて、蝸牛管(かぎゅうかん)といいます。この中にも液が入っていますが、上や下とは違う液なので、内リンパと呼ばれます。
蝸牛管の中には、特別な細胞があって、音の信号を記録し、それを電気信号に変えて、脳へ送ります。
中耳は、音を強める役目をしています。
鼓膜(こまく)の振動は、ここで強められて、知覚器のある内耳へと送られます。
平衡感覚(へいこうかんかく) ②
耳の病気には、いろいろなものがあります。
主な病気と対処法について紹介します。