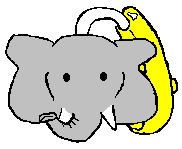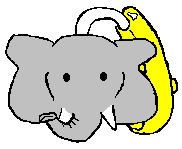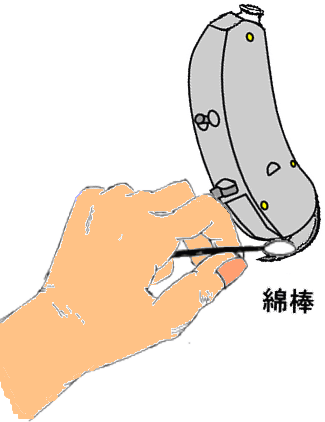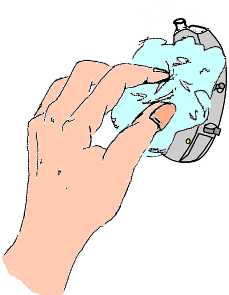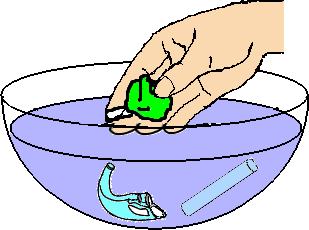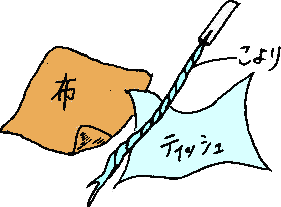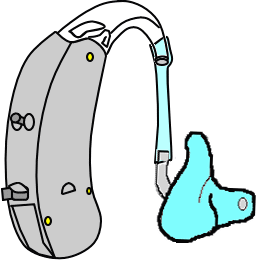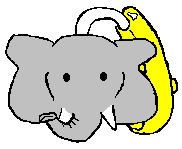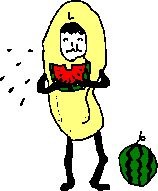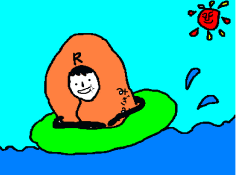毎日暑い日が続くと、何もしていないのに汗が額を流れてきます。 この時期は、補聴器の管理がとても重要です。汗をかいたのに、補聴器をそのままにしていませんか?めんどうだから…と言って、 補聴器をそのままにしていませんか?補聴器の弱点は、実は『汗』。『汗』は補聴器にとって大敵です。 ですから、汗をかく夏は特に補聴器の管理をきちんとしなければなりません。 今回のみみよりでは、もう一度『補聴器の管理』 の方法をおさらいしてみましょう。
○体育やクラブで汗がたくさん出た!
→ すぐに補聴器や自分の耳を拭きましょう。
特に電池室の中も綿棒などで拭きましょうね。
○今日は一日暑かった!寝る前には…
→ 補聴器は電池をはずして、必ず乾燥ケースに入れましょう。
余裕があれば電池室の中を綿棒などで拭きましょう。
○乾燥ケースに入れようとしたら、シリカゲルがピンクになっている…。
一口メモ
~電子レンジでの乾燥~
- 乾燥ケースの中のシリカゲルをお皿などの耐熱容器に広げます。
- 「1分間×3回」を目安に、シリカゲルの様子を見ながら乾燥させましょう。
- まとめて3分間位すると黒焦げになることがありますので注意が必要です。
- また、電子レンジで乾燥させても青に戻らない場合は、シリカゲルが古くなっていますので買い換えましょう。
|
→ シリカゲルがピンクの状態では、乾燥できません!
新しいものに取り替えるか、 シリカゲルが青くなるまで電子レンジで乾燥させましょう。
○電池室がさびている…。
→ 汗をかいた後、そのままにしていた可能性があります。
担任の先生か自立活動部の先生に相談しましょう。
○補聴器を水の中に落とした、洗濯機に入れてしまった…。
→ そんな時もあわてずに!見つけたら、水気を拭きとってから、すぐ乾燥ケースの中に入れましょう。
その後、担任の先生か自立活動部の先生に相談しましょう。
○海水浴に行って、海の中に補聴器を落としてしまった。
→ 海水に含まれる塩分は、補聴器にとって大敵です!
すぐに水道水(真水)で洗いましょう。
その後、乾燥ケースに入れ、学校の先生か、補聴器店に持っていってください。
○補聴器が聞こえにくくなった…。
→ いろいろな原因が考えられますが、イヤモールドの穴に耳垢(みみあか)がつまっていませんか?
10代の若者は新陳代謝が活発で、そのため耳垢もたくさんでます。
それが、夏だともっと活発です。 こまめにイヤモールドの掃除や耳の掃除をしましょうね。
このページのtopへ戻る
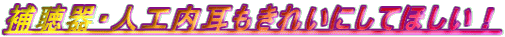
汗ばむ季節になってきました。水や汗が補聴器や人工内耳につくとどうなるのでしょうか。
補聴器や人工内耳は「精密機械」で、たくさんの細かい金属の部品からできています。
この中に水分が入り込むと、金属がさびてしまいます。つながっていた線が切れたり、細い金具が折れたりして、機械が動かなくなって聞こえなくなってしまうのです。
汗をかいた日は、特にきれいに乾燥させましょう。
汗は水だけでなく、塩分が含まれています。汗は水だけより金属がさびやすいのです。
そのままにしておくとしばらくは聞こえても、じきに聞こえなくなってしまいます。
あるデータによると、いつも使っている補聴器や人工内耳の大半(82%)は微生物(細菌など)に汚染されています。補聴器・人工内耳の掃除や耳の掃除をせずに、耳垢などの汚れをそのままにしておくと補聴器や人工内耳の調子が悪くなります。また、様々な病気に罹る原因にもなります。
修理に出すとお金がかかります。自分できちんときれいにしておくこと、故障させないことが大切です。
| 1 |
補聴器本体から、フック、チューブ、イヤーモールドを取り外します。
*人工内耳の場合は機種によって分解の方法が違うので注意して掃除をしてください。
|
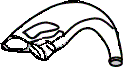
フック
|

チューブ |
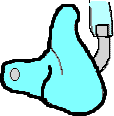
イヤモールド |
| 2 |
補聴器本体をティッシュで拭きます。細かいところは綿棒で掃除しましょう。汚れが取れにくい場合は、アルコールを少し付けて取りましょう。(電池室も忘れずに!)
湿気をふき取ることが大切です。
人工内耳はまた、スピーチプロッセッサやマイクやコードなどは水分に弱いので軽く拭くだけにしましょう。 |
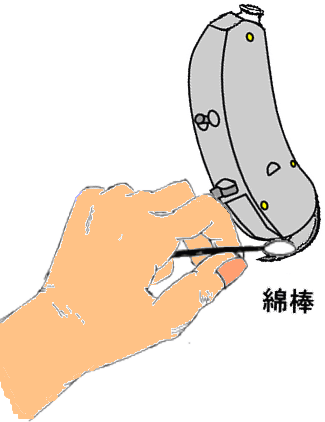 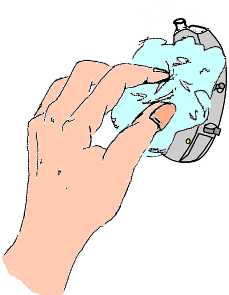 |
チューブ、イヤモールドは水洗いもできます。
フック、チューブ、イヤーモールドはぬるま湯にしばらくつけておきましょう。
ただし、補聴器本体はつけてはいけませんよ!
フックはダンパー(網状の音響抵抗)があるものは洗う時に注意してください。 |

ダンパーを突き破らないように |
| ぬるま湯の中で優しく振り洗いします。汚れの酷いところは歯間ブラシなどを使って洗います。 |
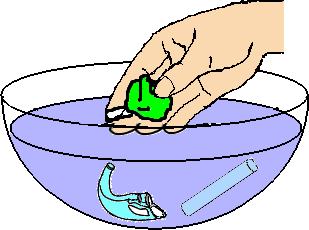 |
きれいにすすいでティッシュで水分を拭き取ります。フック、チューブ、イヤーモールドの中はこより(ティッシュを細くしたもの)で水分を拭き取ってください。
|
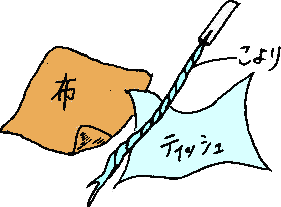 |
| 3 |
きれいにしたら分解したまま、乾燥ケースの中にしまいましょう。
このとき、電池は入れないように! 電池が早くなくなってしまいます。
別のケースに入れておくと、なくすことはないですね。 |
 |
| 乾燥が終わったら組み立てましょう。 |
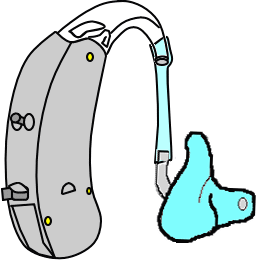 |
高等部の「きこえのコーナー」には超音波洗浄機もあります。
係の先生に言って、使わせてもらうと、簡単にきれいにすることができます。
このページのtopへ戻る
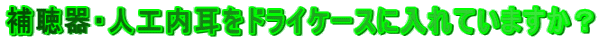
皆さんは寝るときに、補聴器や人工内耳をどこに置いていますか?
補聴器や人工内耳は、複雑な精密機械が使われています。特に湿気に弱く、そのままにしておくと内部の機械が故障する原因になります。
補聴器や人工ない場のマイクの部分は耳に密着させて使います。夏の汗をかく季節はとても湿気による故障が多くなります。しかし、冬でも汗をかくことはありますし、気温が低いために結露現象(窓やガラスに水滴がつくのと同じ現象)が起きて、補聴器の内部のチューブやフックの中に水がたまることがあります。
| 毎日、乾燥剤の入ったドライケースに入れて、補聴器や人工内耳の湿気を飛ばすことが、故障を防ぎ、長持ちさせることになります。 |
 |
乾燥剤は、お菓子などについているものではなく、薬局で販売されているものを使いましょう。(学校でも買うことができます。)中の青い粒がピンク色に変わったら、湿気を取る力がなくなったというサインです。ピンク色になったら、フライパンや電子レンジで加熱すると、また青色に戻って湿気を吸い取れるようになります。(加熱するときは換気をして、専用のフライパンや容器を使いましょう。)使っているうちにだんだん小さくなったり、青色に戻らなくなってくるので、1~2回加熱して小さくなったら取り替えるようにしましょう。
一日中大きな音を出してがんばった補聴器や人工内耳を、夜はゆっくりドライケースの中で休ませ、乾燥させましょう。
このページのtopへ戻る
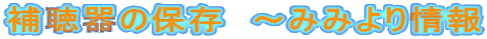
みなさん、補聴器の管理はきちんとやっていますか? 補聴器を保管するとき、ちゃんとケースに入れていますか?ケースに入れたけれど、乾燥剤(シリカゲル)が古くなっているなどの原因で、補聴器の調子がおかしい、聞こえない、などよくあることです。
今回なんと!画期的な補聴器ケースが登場しました。その名も『Quick aid』(クイックエイド)!今までの補聴器ケースとは違い、ハイテクが駆使されたまったく新しい補聴器専用乾燥機です。 |
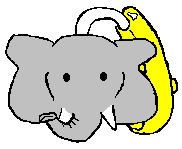 |
 |
Quick aid〔クイックエイド〕
これには、汗や湿気などを素早く乾燥させる循環ファンや、表面についている雑菌などを除菌できる紫外線LED搭載、臭いなども強力に脱臭できるハイブリットシートや特殊乾燥剤が組み込まれています。
ボタン一つで簡単に乾燥・除菌・脱臭ができるすぐれものです!単4電池2つで動くのでとても軽く持ち運びにも楽です。旅行のときに便利ですよ! |
 |
もっと詳しく知りたい人や、実物を見てみたい人は、聴能室にパンフレットと実物が置いてあります。
このページのtopへ戻る
補聴器は、コンピュータ・マイク・スピーカーが内蔵された精密機械であるため、湿気や水濡れには弱いものです。使用した後は乾燥材が入った乾燥ケースに入れておかなければ、故障しやすくなってしまいます。
これからの季節は海やプールなどに行く機会もあるでしょう。また、汗をかきやすい時期でもあります。今回は湿気や水濡れの対策についてお話します。 |
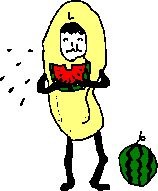 |
|
|
 |
| 【1】汗をかいたとき。雨に濡れたとき |
| ① |
やわらかい布やティッシュなどで、全体を拭き、水分を吸い取ります。
フック・チューブ・イヤーモールドをはずし、水分を吸い取ります。
電池も抜いて拭きましょう。 |
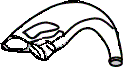  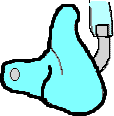 |
| ② |
乾燥ケースに入れてしばらく乾燥させます。
電池(空気電池)は乾燥すると電池の消耗が激しくなるので、乾燥ケースには入れないでください。
ドライヤーの温風で乾かしてはいけません。(精密機械である補聴器は熱に弱いため。) |
 |
| ③ |
音が出ているか確認します。
音が出なかったり、いつもと違う音がしたりする場合は故障の可能性があるので、すぐに学校の先生に相談しましょう。 |
| ○ |
激しい雨の時は補聴器をはずしたほうがよいでしょう。 |
|
|
|
|
|
| 【2】補聴器を洗濯したとき。補聴器をつけたままお風呂に入ったとき |
|
対処法は、汗や雨に濡れたときと同じく、「拭きとり」と「乾燥」を行います。
この場合、ドライケースには、一日ぐらい入れてください。 |
 |
|
汗や雨と違うことは、機械内部まで水分が浸透することです。洗剤やあか、補聴器に付着している皮脂も機械内部に入ってしまいます。
何らかの故障が起きている場合が多いので、学校の先生に見てもらいましょう。 |
|
夏休み期間中など、学校の先生に見てもらえないときは、できるだけ早く補聴器店に持っていき、点検を受けましょう。 |
|
|
|
|
| 【3】海水で補聴器が濡れたとき |
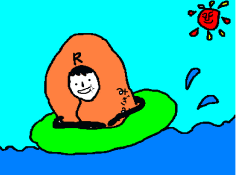 |
| ① |
すぐに水道水で洗います。(海水に含まれる塩分で、機械内部がさびついてしまします。) |
| ② |
【1】【2】と同じく「拭きとり」「乾燥」を行います。 |
|
| ③ |
乾燥ケースに入れ、学校の先生に見てもらうか補聴器店に持っていきましょう。 |
|
このページのtopへ戻る