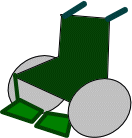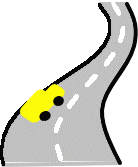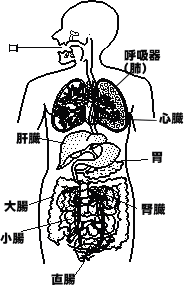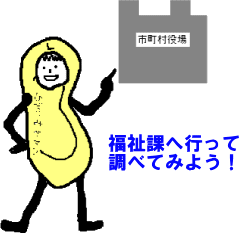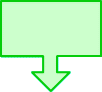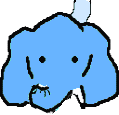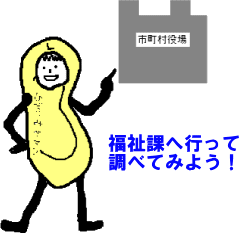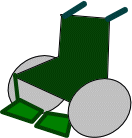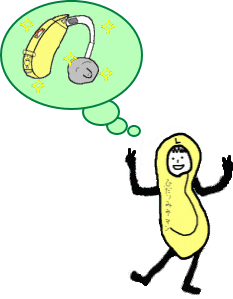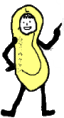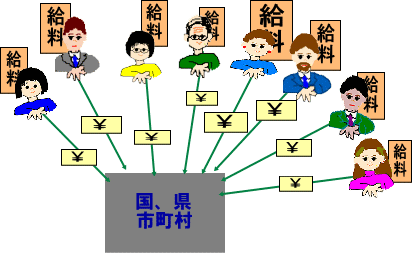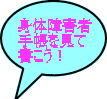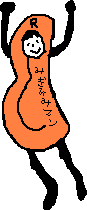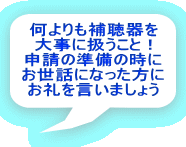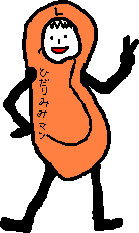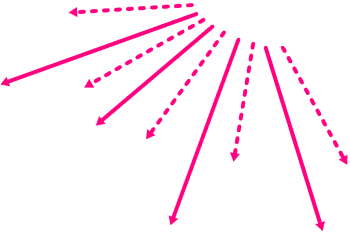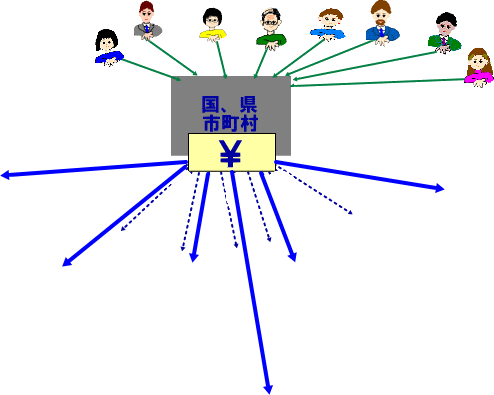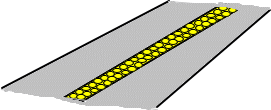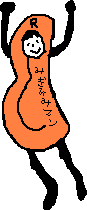「補装具の給付」についてはもう皆さんも利用していると思います。「補装具」とは皆さんが使っている補聴器や,車椅子など障害によって失われた部位や欠陥のある部分を補うための用具のことです。その他にファックスなど,必要な道具の補助金がもらえることもあります。
「公共料金の割引」は皆さんもすでに利用したことがあるのではないでしょうか。JRや,バス,タクシーなど公共交通機関を利用するとき,身体障害者手帳を見せると,料金が安くなりますよね。また,飛行機やフェリー,有料道路(高速道路)などでも同じように安くなります。このとき,あらかじめ市町村役場で,手帳に証明印を受けなければならないこともありますので,地域の市町村役場に確認してください。
また,美術館や映画館など,文化施設の入場料が割引になることもあります。自分が利用する施設に尋ねてみましょう。
「税制上の優遇」とは,納めなければならない税金の控除が受けられる(安くなったり,払わなくてもよくなったりする)ことです。働くようになると,税金を納めなければなりませんね。障害がある人は,所得税(働いている人がもらう給与によって払う税金),住民税(住んでいる,生活している地域に払う税金),自動車税(自動車を持っている人が払う税金)などの控除を受ける(安くなる)ことができます。これにはいろいろなものがありますので,税務署か税理士さんに相談しながら控除される金額等を調べる必要があります。
みなさんは,貯金したことがありますか?貯金をするときに利子がつきますが,その利子に税金がかかっていることを知っていますか?この利子につく税金を非課税(税金がつかないこと)にすることもできます。
身体障害者手帳の給付については前回にお話しましたね。では,今回は給付された「身体障害者手帳」を使ってどんなことができるかを説明します。身体障害者手帳を持っていると,「税制上の優遇措置」,「公共料金の割引」「補装具の給付」が受けられます。
申請するのは,もより(近く)の福祉事務所または,市町村役場の福祉課です。問い合わせてみましょう。
次に,「身体障害者手帳」の手続きについてです。新規(新しく)に申請するときと,変更による再交付申請,紛失(なくしたとき)・破損(破ったり壊れたとき)による再交付の申請をそれぞれまとめてみました。
身体障害者手帳を申請することができる方
| 1 |
上肢,下肢,体幹機能に障害がある方 |
| 2 |
乳幼児期以前に非進行性の脳病変による運動機能障害のある方 |
| 3 |
視覚に障害のある方 |
| 4 |
.聴覚に障害のある方 |
| 5 |
.平衡機能障害のある方 |
| 6 |
音声機能,言語機能またはそしゃく機能に障害のある方 |
| 7 |
心臓機能に障害のある方 |
| 8 |
腎臓機能に障害のある方 |
| 9 |
呼吸器機能に障害のある方 |
| 10 |
ぼうこうまたは直腸の機能に障害のある方 |
| 11 |
小腸機能に障害のある方 |
| 12 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方 |
② 変更(変わったとき), 紛失(なくしたとき)・破損(壊した、破ったとき),返還(返すとき)等
| 必要なもの |
変更
(へんこう) |
紛失
(ふんしつ) |
返還
(へんかん) |
等級
(とうきゅう) |
住所
(じゅうしょ) |
身体障害者手帳
申請書 |
○ |
|
○ |
|
| 医師の意見書 |
○ |
|
|
|
| 身体障害者手帳 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 顔写真1枚 |
○ |
|
○ |
|
| 印鑑 |
○ |
○ |
○ |
○ |
① 新規
必要なもの
身体障害者手帳交付申請書
医師の意見書(診断書)
顔写真1枚
印鑑
「身体障害者手帳」とはどういうものでしょうか。何のためにあるのでしょうか。
身体障害者手帳は,病気やけがなどによって永続的に身体に障害が残ってしまった人がいろいろな福祉制度を受けるために申請をすることができます。障害の程度によって1~7級に区分されています。
福祉制度って何?
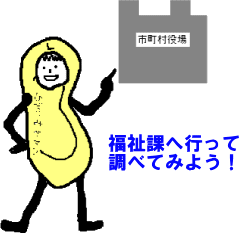
まずは,
①必要な書類を取り寄せます。市町村役場に行ってもらったり,遠い人は手紙を書いて書類を送ってもらうこともできます。その時,係の人に記入するところや,必要な書類を書いてもらうところの説明も受けましょう。
次に
②書類を書きましょう。『
補装具申請書』は,身体障害者手帳を見ながら書きましょう。また,家族のことも書く欄があります。
『
医師の意見書』は病院や,『耳と言葉の教室』で書いてもらうことができます。聴力検査をして,補聴器が必要であることを医師に証明してもらうのです。
次に,
③自分が欲しい補聴器を選びましょう。まず,どんな型の補聴器が良いか考えましょう。
箱型なのか,耳掛け型なのか,耳穴型なのか。耳穴型以外は,イヤモールドも一緒に考えなければなりません。型が決まったら,いろいろな会社のパンフレットやホームページを見て研究しましょう。補聴器は,たくさんの種類があり性能も様々です。自分の聴力レベルに合わせて
希望する機能を考えていきましょう。
補聴器によっては
試聴できるものもありますから業者に依頼して,実際に試聴して決めるのも良い方法です。
自立支援法に対応した補聴器とは…
補聴器が決まったら『
見積書』を希望の補聴器を取り扱っている業者に書いてもらいます。希望する補聴器の金額がいくらするのかを計算してもらいます。
すべての書類が整ったら,身体障害者手帳を持って
④役場に補聴器の申請のために書類を提出に行きます。(遠い人は郵送することもできますが,自立活動部の先生と相談して手紙を同封しましょう。)
書類を受け付けてもらったら,1~2ヶ月して
⑤申請の許可が下りてきます。役所から連絡の手紙がきます。見積書を書いてもらった業者からも連絡があります。イヤモールドが必要なときは,耳型を取ってもらいに行きます。このとき,付属品やオプションなど必要なものがあるときは,一緒に注文すると良いでしょう。
希望するイヤモールドと補聴器が出来上がるとあなたの手元に
⑥補聴器が届きます。差額を払ったら、補聴器はあなたのものです。大切に使いましょう。
高等部の生徒の皆さんは新しい補聴器を申請するとき、先生と一緒に申請のしかたを勉強しながら自分で申請をする練習をしています。学校を卒業した後は、自分で補聴器の申請手続きをすることになるからです。これまでは家の人や学校の先生に任せていた人は、自分が使う補聴器ですから、次の申請のときは少しでもチャレンジしてみませんか?
みなさんは、補聴器が古くなって新しい補聴器が欲しいとき、どうしていますか?自分で補聴器の申請をしたことがありますか?
新しい補聴器は1つで7万円から、高いものは30万円をこえるものもあります。補聴器を両耳につけるためには2つ必要ですから、簡単(かんたん)に買えませんね。そこで、補助金をもらう方法があります。
身体障害者手帳を持っている人は世帯(せたい)の所得(しょとく)(家族の給料の額(がく))によって補聴器の代金の一部(または全額(ぜんがく))が補助(ほじょ)(税金によって代わりにお金を払ってもらうこと)されます。前の補聴器を申請してから5年が過ぎると申請(申込)することができます。そのためには次のような手続きをしなければなりません。自立活動部の先生と相談しながら、自分で補聴器の申請にチャレンジしてみましょう。
なかったら病気のとき困るよね。
たくさんあるもんね。
補聴器って、
1個○万円するって。。。
ぼく、新しい補聴器が欲しいんだけど…
皆さんに補聴器が届くまでの流れはこのようになっているのです。
税金から払われていたなんて知らなかった。
清潔に暮らせるね
きれいな水が使えるね
お年寄りの介護もあるね
車いすが必要な人もいるね
点字ブロックもできるんだ
僕の補聴器はこうやって届くんだね。
税金の使い道はたくさんあるんだね
みんなから集められたお金は、何に使われるのかなぁ?
みんなの給料から税金が納められるんだね。
皆さんも卒業して働くようになると税金を納めますね。税金は,みんなからお金を集めて必要なものに使われます。
では、福祉に使われるお金がどこから出るのか、見てみましょう。
皆さんは補聴器をつけることで周りの音やことばが聴き取りやすくなりますね。
では、その補聴器は…
すべての人がともに協力し合って社会生活を送るには,援助が必要な人もいます。「福祉制度」はみんなで助け合って援助が必要な人には援助しようという考え方から生まれたものです。
障害があると学校に通えなかったり,働くことができなかったり,様々なことができない時代がありました。それを障害者も尊重(そんちょう)され,ともに社会生活が送れるようにさまざまな運動が行われ,少しずつ改善されていったのです。まだ十分とはいえませんが少しずつ変わってきています。法律(ほうりつ)や環境だけでなく,周りの人の障害者に対する理解も大切だと思います。
|
補聴器申請の流れ |
|
|
|
 |
|
家族と相談する |
|
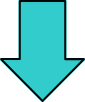 |
|
学校の先生と相談する |
|
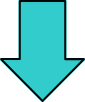 |
|
①書類を揃える |
|
|
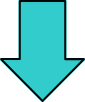 郵送、または直接行ってもらう 郵送、または直接行ってもらう
|
|
| 申請書 |
医師の意見書 |
見積書 |
その他
(申立書など) |
②自分で書く
|
②医師に書いてもらう
「耳とことばの相談」では、無料で書いてもらうことができます。 |
③補聴器を選ぶ
自分に合った補聴器を選ぼう
・業者を選ぶ
・業者に書いてもらう |
②家族と相談して書こう |
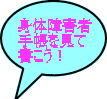 |
|
自立支援法に対応した補聴器とは… |
|
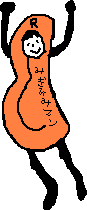 |
④役所に上記の書類をすべて提出する |
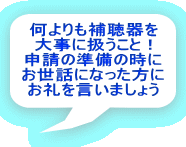 |
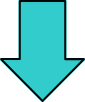 郵送、または持参する 郵送、または持参する |
⑤役所から申請が下りる
(注) 役所から手紙が届く |
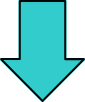 |
| 業者で耳型取りをする |
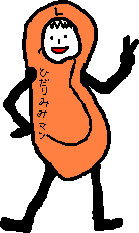 |
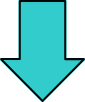 |
|
⑥補聴器が届く
残金(補聴器代と補助金の差額)を払う
差額がなくても1割負担があります。 |
みなさんは「福祉制度(ふくしせいど)」が,何か知っていますか?「福祉制度」というのはすべての人が「幸福で安定した」生活がおくれるように,何らかの障害があり援助(えんじょ)が必要な人を支える制度です。