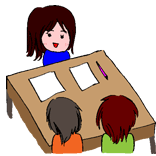

きこえや言葉に困っている方すべてを対象に相談を行っています。
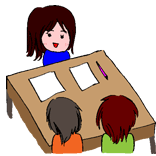 |
 |
| きこえや言葉に困っている方すべてを対象に相談を行っています。 |
|
| 乳幼児教育相談 |
お子さんの聴こえや言葉の発達について、不安や疑問をお持ちの方
いつでもお気軽にご相談ください。
| ●個別相談 | きこえに関するさまざまな相談に応じます。子供とのかかわり方や、家庭でどのような配慮をしたら良いかなど具体的にアドバイスします。。 | |
| ●グループ活動 | 季節の行事や誕生会などの活動を行っています。同年齢での子ども同士が関わりを持てる場にもなっています。 | |
| ●学習会 | 週一回、言葉の育つしくみ・育児・しつけ・栄養・補聴器の管理・聴覚活用の方法などさまざまな分野の学習を行っています。 | |
| ●その他 | インテグレート児(ろう学校から地域の幼稚園、保育園(所)へ転園した幼児)、本校在籍でない乳幼児のことばの育て方、補聴システム、就学などさまざまな悩みの相談も受け付けています。 |
| 就学・教育相談 |
| 就学や学校生活全般について、不安に感じていることなどご相談ください。 担当者が相談内容に応じて、対応します。 (本校は、幼稚部・小学部・中学部・高等部があり、各学年に対応した相談ができます。) 状態に応じて定期的な指導を行うこともあります。 |
| 補聴器ときこえの相談 |
| 聴覚障害についての相談にのります。 本人が来られたときは、聴力レベルを知るために聴力測定を行います。 補聴器についても新しく補聴器をつける(新規購入)際のお手伝いをしたり、管理についての相談にのります。 補聴器の調整(フィッティング)や修理の相談にのります。 |
| 新生児 | 生後3週間以内ならほぼ確実な測定が簡単にできます。 | ||||||||
| 0〜2歳 | きめ細かい観察をして音に対する反応を測定します。 (ABR【脳幹反応検査】で正しい結果が出ないこともあります。) |
||||||||
| 2歳〜 | COR【遊戯能力検査】・条件検索反応検査などを行うことができます。 簡単な装置で、子どもたちも楽しんで検査を受けることができます。 |
||||||||
| 4歳〜 | 標準の聴力測定ができます。 (ただし大人のように集中力がありませんので、本当の聞こえよりも少し悪い数値が出ることがあります。) 
|
| 補聴器の使い始め | ||
| 選択 | 聴力測定の結果を元に、そのきこえにあった補聴器の選択のお手伝いをします。 箱型、耳掛け式、耳穴式、骨導型、デジタル式、FM式などさまざまな補聴器があります。 【高等部生には自分で申請ができるように申請の方法についても指導します。】 |
|
| 調整 | 聴力の特性に合わせて、出力や音質、不快レベルなどの調整をします。 | |
| フィッティング | 補聴器装用時聴力測定の結果をも対応しながら、微調整をしてよりよい聞こえにします。 イヤモールド【耳型イヤフォン】の修正なども行います。 |
|
| 補聴器を使い続けていくためには | ||
| ことばが育つためには補聴器を通じての聞こえができるだけよい状態であることと、その聞こえがいつも同じように聞こえる必要があります。 いつも同じように聞こえて、それを何度も聞いて音の変化のパターンを大脳の神経回路が認識するようになるという原理があるからです。そのために補聴器の管理がとても大切となります。 |
||
| 管理 | 補聴器特性検査装置を使って、一人一人にあった補聴器の調整を行い、そのデータを保存します。 いつでもそのデータを取り出し、補聴器の正確な管理を行うことができます。 補聴器の使用法、日常の手入れ、保管、簡単な修理の方法など具体的な指導を行います。 |
|
| 修理 | 補聴器の修理ができる専門の技術者がいますので、簡単な修理なら短期間で行うことができます。 イヤモールドの修理や修正も行います。ハウリング【音響的フィードバック】を止めるノウハウもありますので、お困りの方はご相談ください。 |
|
| 補聴器を使っても効果がないくらいに重度の難聴の場合でも、人工内耳によって聞こえを取り戻すことができます。 人工内耳は手術が必要なことや、術後の機器の調整、リハビリの方法などによって効果が大きく左右されることなどから、医療機関との密接な連携が必要です。 本校では、手術を行う大学病院や術後の機器調節やリハビリを行っている医療機関と情報交換を行いながら教育を進めています。 数多くの実績や実践、最新の情報など豊富にもっていますので、人工内耳について詳しく知りたい方、手術を考えておられる方などぜひご相談ください。 |
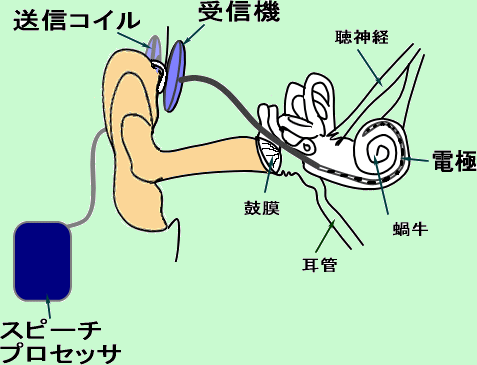 |
| 関係者(担任の先生など)の相談 |
|
聴覚に障害があるお子さんや生活の中で気になるお子さんとかかわりのある方への支援を行っています。 相談内容をお伝えください。 |
||||
| ○ 幼稚園・学校などへ訪問し、気になるお子さんの生活を見せていただき、対応を一緒に考えます。 | ||||
| 幼稚園・学校でどのように過ごしているか・環境などを見せていただきます。 生活の中での配慮する点 教室の中で配慮する点 一緒に生活する子供たちへの説明の方法など |
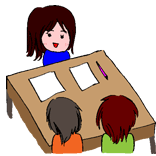 |
|||
| ○ 諸検査を行い、気になるお子さんの実態を把握し、支援方法を検討します。 | ||||
| 聞こえの状態を知るための聴力測定 言葉をどれくらい聞き取ることができるかを知るための語音聞き取り検査 発達の諸側面を知るための各種発達検査など |
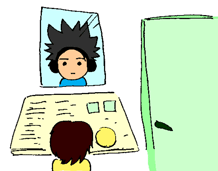 |
|||
| いずれも保護者の方の了解を得てから実態や相談内容に応じて行います。 | ||||
| ○ 気になるお子さんを理解するために、説明会や研修会の講師を派遣します。 | ||||
| きこえにくい子どもと接する先生向けの研修会 きこえにくい子どもと接する周囲の子供たち向けの学習会 保護者向けの説明会 地域の方向けの研修会 |
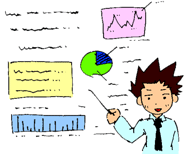 |
|||
| など | ||||
| クラス・学年・学校単位で行うなど、相談に応じて行います。 教育関係機関以外に、自動車学校などでも行いました。 |
||||
その他にも相談内容によって、支援を行います。