| 明治41.9 | 長崎県水産講習所を北松浦郡平戸町(平戸市)に設立する。 |
| 44.7 | 長崎県水産講習所を長崎市に移転する。 |
| 昭和10.3 | 長崎県水産講習所を廃止する。 |
| 10.4 | 長崎県立水産学校を長崎市丸尾町に設立する。生徒定員150名。 |
| 12.4 | 長崎市土井の首町に移転する。 |
| 18.3 | これまでの設置課程である漁撈、製造の2科の他に経営科を設置する。 |
| 23.4 | 学生改革により長崎県立長崎水産高等学校を設立する。 設置課程を漁業、水産製造、水産経営の3科とし、定員を各120名、合計360名と する。 同時に本校内に定時制中心校(漁業・水産製造課程)、五島・平戸・対馬の各高等学校内に分校(水産課程)を設置する。 |
| 23.12 | 定時制対馬分校を上県郡豊崎町比田勝中学校内に豊崎分校として移転する。 |
| 24.4 | 定時制野母分校(水産課程)を西彼杵郡野母村立野母中学校内に設置する。 |
| 24.5 | 定時制奈留島分校(水産課程)を南松浦郡奈留島村立奈留島中学校内に設置する。 |
| 25.6 | 定時制鷹島分校(水産課程)を北松浦郡鷹島村立鷹島中学校内に設置する。 |
| 26.6 | 定時制奈留島分校を廃止する。 |
| 27.3 | 定時制豊崎分校を対馬高等学校に移管する。 |
| 28.5 | 実習船長水丸(鋼製、総屯数179.8屯)竣工する。 |
| 29.3 | 定時制中心校を廃止する。 |
| 30.3 | 定時制野母分校を廃止する。 定時制鷹島分校を平戸猶興館高等学校に移管する。 |
| 31.3 | 漁業専攻科を設置する。定員20名。 |
| 32.4 | 水産増殖科を設置する。1学年定員20名。 |
| 33.10 | 本校創立50周年記念式典を挙行する。 |
| 35.4 | 漁船機関科を設置する。1学年定員40名。 |
| 40.4 | 無線通信科を設置する。1学年定員40名。 |
| 41.4 | 漁船機関科を機関科に改称する。 |
| 42.3 | 第2代長水丸(鋼製、総屯数364.67屯)竣工する。 端艇2隻を建造する。 |
| 42.4 | 水産増殖科の定員を40名とする。 |
| 43.4 | 機関専攻科を設置する。定員20名。 |
| 45.4 | 水産経営科を漁業経営科に改称する。 長崎市磯道町5番地より長崎市末石町157番地1に移転する。 |
| 48.12 | 乙種二等航海士第一種養成施設として認定される。 内燃機関乙種二等機関士第一種養成施設として認定される。 |
| 49.1 | 甲種二等航海士第一種養成施設として認定される。 内燃機関甲種二等機関士第一種養成施設として認定される。 |
| 51.9 | 小型実習船すいらん(総屯数19.24屯)竣工する。 |
| 53.11 | 本校創立70周年記念式典を挙行する。 |
| 54.3 | 第3代長水丸(総屯数476.75屯)竣工する。 |
| 55.3 | 西彼杵群三和町に臨海実習場を竣工する。 推薦入学制度を発足する。 |
| 56.1 | 乙種一等航海士第一種養成施設として認定される。 |
| 3 | 三級海技士(航海)第一種養成施設として認定される。 三級海技士(機関)第一種養成施設として認定される。 四級海技士(航海)第 一種養成施設として認定される。 四級海技士(機関)第一種養成施設として認定される。 |
| 63.5 | 全国水産高校SUIKO-VANに加入する。 |
| 63.12 | 第3級無線通信士の予備試験・英語・電気通信術の免除を認定される。 |
| 平成元.11 | 本校創立80周年記念式典を挙行する。(昭和63年を延期) |
| 3.4 | 無線通信科を情報通信科へ学科改編する。 |
| 5.3 | 第4代長水丸(総屯数492屯)竣工する。 |
| 5.8 | 工事担任者アナログ第三種試験の一部免除を認定される。 |
| 8.4 | 学科改編を行い、漁業科と水産製造科、漁業経営科の募集を停止。 海洋科と食品流通科を設置する1学年定員各40 名。 |
| 9.3 | パソコン41台を更新する。 |
| 10.11 | 創立90周年記念事業挙行。 |
| 18.4 | 学校改革に伴い、海洋科、食品流通科、水産増殖科、機関科、情報通信科の募集を停止。 水産科と総合学科を設置し、校名も長崎県立長崎水産高等学校から長崎県立長崎鶴洋高等学校へ。 1学年水産科3クラス定員120名、総合学科3クラス定員120名。 |
| 20.9~11 | 創立100周年記念事業挙行。 |
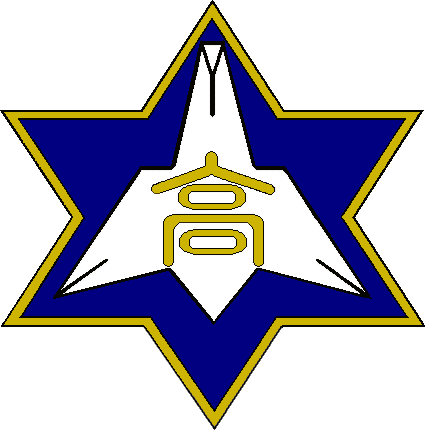 Nagasaki Kakuyo High School
Nagasaki Kakuyo High School 長崎県立長崎鶴洋高等学校
長崎県立長崎鶴洋高等学校
(旧長崎県立長崎水産高等学校)
〒850-0991
長崎県長崎市末石町157番地1
TEL 095-871-5675
FAX 095-871-5488